【初回60分無料相談】大阪で遺産分割に強い弁護士をお探しなら

遺産分割に関するみんなのお悩み

所在が不明な相続人がいて遺産分割ができない。



遺産分割調停を申し立てられてしまって対応が分からない。



不動産の評価額が決まらない。



遺産分割協議書の作成方法が分からない。



一部の相続人が生前に多額の贈与を受けていた。遺産分割に反映させたい。



相続預金の使い込みの有無を調べたい。
代表弁護士


Leapal法律事務所の代表弁護士の山村真吾です。
当事務所では、案件を大量に処理するのではなく、限られた依頼者一人ひとりに誠実かつ質の高いリーガルサポートを提供することを信条としています。
相続には複雑な法律問題が絡むため、個々の状況に応じた専門的な対応が不可欠です。当事務所では、法的な知識はもちろん、感情的な対立にも配慮しながら、円満な解決を目指す姿勢を大切にしています。
相続問題で悩まれている方、または不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。弁護士として、皆様のお力になれることを心より願っています。
お悩み①遺産分割の進め方が分からない



親が亡くなって相続が始まったんですが、どうやって遺産分割を進めたらいいのかわかりません。何から始めればいいのでしょうか?



相続が発生した際、まず初めに確認すべきは「遺言書の有無」です。
⑴遺言書がある場合
遺言の内容に従って相続手続きを進めることが原則です(ただし、全相続人の合意があれば一部変更も可能です)。
⑵遺言書がない場合
相続人全員による「遺産分割協議」が必要となります。話し合いがまとまったら、内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、それに基づいて各財産の名義変更などの手続きを進めていきます。



遺産分割協議には、誰が参加する必要がありますか?



遺産分割協議には、「法定相続人全員」の参加が必要です。
相続人の範囲は以下のように定められています
⑴配偶者(常に相続人となります)
⑵子ども(子が死亡している場合はその子=孫が代襲相続人になります)
⑶子どもがいない場合は、直系尊属(親・祖父母)
⑷それらもいない場合は、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、その子=甥・姪が代襲相続人になります)
相続人の確定は、遺産分割協議の出発点です。必ず戸籍を収集して正確に確認する必要があります。



遺産分割協議には期限がありますか?



法律上、遺産分割そのものには明確な期限はありません。
ただし、注意が必要なのは相続税の申告期限です。相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日から10か月以内に手続きする必要があります。
申告期限までに遺産分割がまとまっていないと、税務上の特例が使えないこともあります。
そのため、協議はなるべく早めに着手することが望まれます。



話し合いがまとまらないときはどうすれば?



相続人の中に協議に応じない人がいたり、意見がまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てを行うことになります。
調停では、裁判所が選任する調停委員が間に入り、相続人間の意見を調整します。
合意に至れば、「調停調書」が作成され、それは確定判決と同様の法的効力を持ちます。
それでも合意に至らなければ、次は審判手続に移行し、裁判官が最終的な遺産分割方法を判断します。
※相手方が大阪府内に住民票上の住所を有しているのであれば、申立先の家庭裁判所は以下のとおりです。
| 堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村) 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市 | 大阪家庭裁判所堺支部 |
| 岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡(忠岡町) 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡(熊取町 田尻町 岬町) | 大阪家庭裁判所岸和田支部 |
| 上記以外 | 大阪家庭裁判所 |



話し合いを始める前に、どんな準備をしておくといいですか?



遺産分割協議を円滑に進めるためには、次のような準備が重要です
⑴遺言書の有無を確認(ある場合は内容の確認と検認手続)
⑵相続人の確定(戸籍の調査によって確認)
⑶遺産内容の把握(預貯金・不動産・有価証券・債務などを調査)
⑷財産目録の作成(遺産内容を一覧にまとめておく)



結構やることが多いですね。
協議がまとまったら、次は何をすれば?



相続人全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成します。
この書面には以下の内容を明記します:
各相続人がどの財産を取得するか
相続税や費用の分担方法
後日、新たな遺産が発見された場合の対応
協議書に基づき、不動産登記の名義変更や銀行の手続き等を行います。



協議書は自分たちで作成しても大丈夫ですか?



自分たちで作成することも可能ですが、形式の不備や内容の不明確さによって、名義変更手続が進まないことや、後日トラブルになることもあります。
そのため、署名・押印をする前に、弁護士や司法書士によるチェックを受けることを強くおすすめします。
相続手続きは、法律的にも実務的にも複雑です。
「何から始めればよいか分からない」「家族間で意見がまとまらない」といったお悩みがある場合には、早めに専門家にご相談ください。
当事務所では、遺産分割協議のサポートはもちろん、調停・審判への対応まで一貫してお手伝いしております。
初回無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
お悩み②不動産や株の分け方で悩んでいる



相続財産の中に不動産や株式が含まれていて、どう分けるのが公平なのか悩んでいます。現物をそのまま分けるのは難しいし、相続人全員が納得する方法が見つかりません。



不動産や株式のように「現物を等分できない財産」は、相続人全員の合意を前提に、以下のような分け方が検討されます
⑴換価分割:不動産や株式を売却し、得られた代金を相続分に応じて分ける
⑵代償分割:特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に「代償金(現金)」を支払う
⑶共有分割:複数の相続人が共同名義で財産を所有する
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご家庭の状況や相続人のご意向に応じて、最適な方法を検討する必要があります。当事務所では、ご事情を伺いながら丁寧にサポートいたします。



不動産を売却して分けることはできますか?



はい、「換価分割」と呼ばれる方法です。
これは、実務でもよく使われる分割方法で、以下のようなケースで特に有効です
・相続人の誰もその不動産を使う予定がない
・不動産の評価額について意見が分かれている
売却後は、その代金を法定相続分または協議で定めた割合に従って分配します。



不動産を売却して分ける場合のデメリットはありますか?



いくつか注意点があります
⑴買い手が見つからなければ分割できない
→特に地方の土地や利用価値が低い不動産は、売却が難航することがあります
⑵売却費用がかかる
→不動産仲介手数料、登記費用、場合によっては譲渡所得税などが発生するため、手元に残る金額が想定より少なくなることがあります
そのため、売却に頼らず、他の方法を検討することも重要です。



代償分割とはどのような方法ですか?



代償分割は、不動産などの財産を相続人の一人が取得し、その代わりに他の相続人へ代償金(現金)を支払う方法です。
たとえば、長男が実家を相続し、その評価額に応じて兄弟に代償金を支払う、といったケースが典型です。
不動産を売却する必要がないため、住み続けたい人がいる場合などには有効な方法です。



代償分割のデメリットはありますか?



⑴代償金の準備が必要
→財産を取得する相続人が高額の現金を用意しなければならず、負担が重くなることがあります
⑵不動産の評価に争いが生じやすい
→評価額に納得が得られないと、合意形成が困難になります
実現可能性や資金調達の見通しを慎重に検討したうえで進めることが大切です。



株式の分割はどうなりますか?



上場している株であれば市場価格があるため、基準が明確でトラブルになることは少ないと思います。
他方で、非上場の株式の評価は、評価が非常に難しく、相続人間で大きな対立が生じることがあります。経営権や議決権の問題も絡むため、専門的な対応が必要です。
非上場株の相続でお悩みの場合は、早めに弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
お悩み③音信不通だった相続人が突然現れた



何年も連絡が取れなかった親戚が、突然『自分にも相続権がある』と主張してきました。他の相続人とも意見がぶつかり、話し合いが進まず困っています。



音信不通だった相続人であっても、法律上、他の相続人と同様に正当な相続権を持っています。したがって、その方が相続分を主張すること自体は法的に認められています。
しかし、突然の主張によって他の相続人との信頼関係が崩れたり、感情的な対立が生じたりするケースも少なくありません。その結果、遺産分割協議が停滞することは多々あります。
当事務所では、そのような場合でも当事者間の関係を冷静に整理し、法的な立場を明確にしたうえで、公平・円満な解決に向けた交渉を進めていきます。第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けながら話し合いを進めることが可能です。



他の相続人が話し合いに応じてくれない場合はどうすればいいですか?



相続人のうち一部が話し合いに応じず、協議が成立しない場合でも、手がないわけではありません。
そのようなときは、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停では、裁判所が選任する調停委員が間に入り、相続人全員の意見を調整しながら合意形成を目指します。
さらに、調停でも解決が図れない場合には、「審判手続」へ移行し、裁判所が法定相続分や事情を考慮して、最終的な遺産分割方法を決定します。



当事務所では、まずは協議による円満解決を第一に考え、相続人間の橋渡し役として、冷静かつ適切な交渉を行います。
また、協議での解決が困難な場合には、調停・審判など裁判所手続への対応も全面的にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください!
遺産分割を検討している方へ
- 他の相続人が話し合いに応じてくれない
- 不動産の分け方で揉めている
- 遺産分割をしたいけど、音信不通の相続人がいる
このような方は、是非、ご相談ください。
当事務所では、遺産相続の問題に関して初回60分無料相談を行っています。
<当事務所の対応実績>
・収益不動産等の多数の不動産を含む自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成
・相手方相続人よる遺産の使い込みが問題となった遺産分割交渉事件
・夫婦で互いに相続財産を相続させる旨の公正証書遺言作成
・相続財産の一部を相続人以外の者に遺贈する旨の公正証書遺言作成
・多数の資産を有する中小企業経営者一族の遺産分割(交渉・調停)
・遺言の有効性が争いにになった遺産分割交渉事件
・不動産評価額が争いになった遺留分侵害額請求事件(被請求側 交渉・訴訟)
・遺言によって多数の不動産を相続した相続人に対する遺留分侵害額請求(請求側 交渉・調停)
・相続発生後3か月経過後の相続放棄申述受理申立事件
・相続発生後15年以上経過後の相続放棄申述受理申立事件
・第8回 遺言・相続全国一斉相談会 担当弁護士
・大阪弁護士会主催「分野別登録弁護士による法律相談会」遺言相続 担当弁護士
等
遺産分割の料金表



当事務所の遺産分割の料金表は次のとおりです!
あくまでも弁護士費用を決める目安です。
ご依頼の前に、個別の事情をお伺いし、事前に正式な見積書を提示させて頂きます。
遺産分割交渉の代理
| 遺産総額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
| 1000万円以下 | 20万円 | 獲得した経済的利益の10% |
| 1000万円以上3000万円まで | 30万円 | |
| 3000万円以上1億円まで | 40万円 | |
| 1億円以上 | 50万円 |
遺産分割調停・審判
| 遺産総額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
| 1000万円以下 | 30万円 | 獲得した経済的利益の10% |
| 1000万円以上3000万円まで | 40万円 | |
| 3000万円以上1億円まで | 50万円 | |
| 1億円以上 | 60万円 |
※裁判所への出頭回数(電話期日及びWEB期日を含む。)が通算5回を超えた場合、超過1回につき2万円の日当を請求させて頂きます。
遺産分割に関するよくある質問
- 相談時には何を持参すればよいでしょうか。
-
ご自身の現在の戸籍謄本及び被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、持参をして頂けますとその後の対応がスムーズになります。
- 遺産分割の解決にはどのくらい時間がかかる?
-
ケースバイケースです。
当事務所は、早期解決が依頼者の利益になると考えていますので、できる限り早期に解決ができるように尽力させて頂きます。
- 相続人調査や相続財産調査も依頼できますか?
-
遺産分割をご依頼いただいた場合には、相続人調査、相続財産の調査もさせて頂きます。
また、必要応じて、生前贈与の有無なども調査させて頂きます。
- 相続人が音信不通、所在不明の場合でも依頼は可能ですか。
-
可能です。
- 対応地域はどこになりますか?
-
遺産分割については、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県の近畿4府県で対応しています。
ご依頼の流れ



ご依頼の流れは以下のとおりです!
当事務所公式アカウントから相談予約をお願い致します。相談日程を調整させて頂きます。
初回相談を踏まえて、見積書を提示させて頂きます。もちろん、費用はかかりません。
見積にご納得いただけた場合には、委任契約書を締結させて頂きます。
着手金の振り込みを確認できましたら、事件に着手させて頂きます。
事務所概要・アクセス


| 事務所名 | Leapal法律事務所 |
| 代表弁護士 | 弁護士 山村 真吾 |
| 所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2階 |
| 電話番号 | 06-7777-3890 |
アクセス方法
京阪本線・Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩4分(京阪本線からお越しの場合は西0号改札口、御堂筋線からお越しの場合は北改札をご利用ください)
京阪中之島線「大江橋」駅徒歩3分
JR「北新地」駅徒歩7分(JR「北新地」駅東出口をご利用ください)



気軽に相談してくださいね!















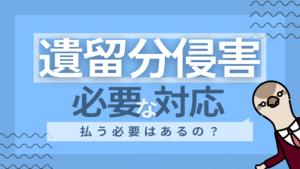
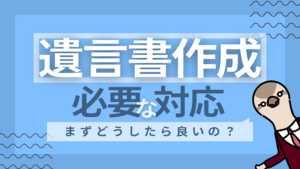


コメント